
喪中はがきはそうそう出す機会もないものですからいざ出そうと思ったら色々と疑問が出てくると思います。
今回は喪中はがきに関する色んな、ちょっとした疑問を解決します。
葬儀に参列してくれた人には送る?送らない?
結論としては、参列してくれた人にも喪中はがきを送ります。
喪中はがきは「身内の○○が亡くなりました」と伝える為のはがきではありません。「新年をお祝いする気持ちではないので今度のお正月は年賀状を出しません」と伝える為に出すものです。
とすると、葬儀に参列したか否かと年賀状を出さないということは一切関係がありませんよね。
喪中はがきを出す相手は、これまで年賀状を出していた相手です。つまり「身内の不幸がなかったらいつも通り年賀状を出していたはずの人」に送るということです。
そう考えれば葬儀に参列していたかしていないか、そこは考える必要がないということがわかりますね。
自分が出す前に先に喪中はがきを受け取った場合
先に喪中はがきを受け取ったとしても、その相手にも喪中はがきを出します。
その際には一言お悔やみの言葉を、「○○様のご逝去心よりお悔やみ申し上げます」と添えると良いでしょう。
2人以上亡くなった場合は?
1年の内に2人以上の身内が亡くなる場合も、あるかもしれませんよね。
喪中はがきには必ずしも故人の情報を載せる必要はありませんが、載せる場合2人以上の名前が書いてあっても問題ありません。
その場合は亡くなった順に記載しましょう。
例えば4月に母が、10月に祖父が亡くなったとしたら
4月に母○○が永眠しました
10月に祖父○○が永眠しました
という風になります。
文書を書き足すのはアリ?
基本的に、喪中はがきの文面に書き足すことはしません。
印刷されたものだったりテンプレート文などありますが、あの文章の中に情報は過不足なく盛り込まれています。加筆するのは故人の名前や年齢くらいです。
喪中はがきの目的は身内の不幸の為新年の挨拶を欠礼しますと伝えるもので、そこに「お元気ですか、今度食事に行きましょう」だとか「引っ越しました、遊びに来てね」など書くのは本末転倒です。
もしも書き足すことがあるとすれば、それは、先述のようなお悔やみの言葉だったり、葬儀に参列してもらったお礼の言葉くらいです。
[quads id=1]喪中はがきの日付より前に出すのはアリ?
11月中に喪中はがきの準備をしてはがきには12月と記載した場合は、12月に届くように出しましょう。
絶対にダメということではないですが、12月でもないのに12月と書いてあったらおかしいですよね。
まぁ実際にそこまで気にして見ている人はそういませんが、記載した日付で届くように出しましょう。
喪中はがきは薄墨を使うもの?
喪中はがきに薄墨は使いません。
不幸にまつわる出来事で薄墨を使うのはなぜか。
本来、墨はするのに時間がかかるものです。丁寧に、時間をかけてすって濃い墨になります。
しかし不幸とは突然に起こるものです。急な知らせをしなければいけない、訃報を聞いて慌てて準備をし大急ぎで駆けつけました、こういう状態の時にゆっくりと丁寧に墨をすっている時間はありません。結果薄い墨で書かれたものとなり、仏事に関しては薄墨が使われるようになったのですね。
ですが喪中はがきは、訃報とは別物です。そもそも喪中はがきは誰かの不幸を知らせる手紙ではありません。故人の詳細も必ずしも書く必要はないです。
喪中はがきとは悲しみの内にあるから年始のご挨拶は控えさせて頂きます、そういう連絡をする役割のものですから、薄墨で書く必然性はないということになります。

はがきの両面に住所氏名は必要?
差出人の住所や氏名は片面のみ書けば良いです。
書いてはいけないという訳ではありませんが、二重に書く必要はありませんよね。
どちらか一方に書いてあれば充分です。
喪中はがきに関する疑問あれこれ まとめ
いかがでしたか?
喪中はがきに関しての疑問は解決できましたでしょうか。
ぜひ参考にしていただけたらと思います。
関連記事
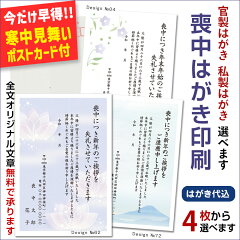

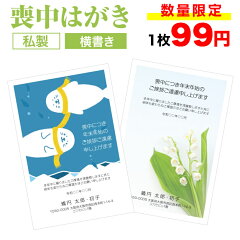


コメント